糖尿病で障害年金を受給するために大切なポイント

糖尿病は国民病ともいわれるほどに、日本人にとって珍しくはない病気です。
糖尿病にかかると日常生活上で気を付けることも多く、また、各種合併症の不安もあります。
糖尿病と付き合っていくには医療費面の不安も募るところですが、糖尿病で障害年金を受給することはできるのでしょうか。
このブログでは、障害年金における糖尿病の認定基準を紹介しています。
ぜひ、最後までお読みください。
目次
糖尿病は国民病?

糖尿病はいまや国民病といわれているのをご存知ですか?
e-ヘルスネットによると、国民の10人に1人は糖尿病にかかっているという驚きの割合。急速な増加の背景には、生活習慣と社会環境の変化が指摘されています。
その一方で、糖尿病から様々な合併症が引き起こされることが懸念されるにもかかわらず、適切な治療を受けているのは糖尿病罹患者の約半数という指摘もされています。
そもそも、糖尿病とはどんな病気なのでしょうか。厚生労働省HPより抜粋します。
糖尿病の病型は、(1)1型糖尿病、(2)2型糖尿病、(3)その他、(4)妊娠糖尿病に大別できる。糖尿病の発症要因としては、遺伝的要因と環境要因が重要であるが、特に2型では生活習慣が環境因子として重要である。我が国の糖尿病の大部分をしめるものは2型糖尿病である。
日本人を対象とした横断的/経年的疫学研究による糖尿病の発症危険因子は、1)加齢、2)家族歴、3)肥満、4)身体的活動の低下(運動不足)5)耐糖能異常(血糖値の上昇)であり、これ以外にも高血圧や高脂血症も独立した危険因子であるとされている
糖尿病で障害年金を受給するためには
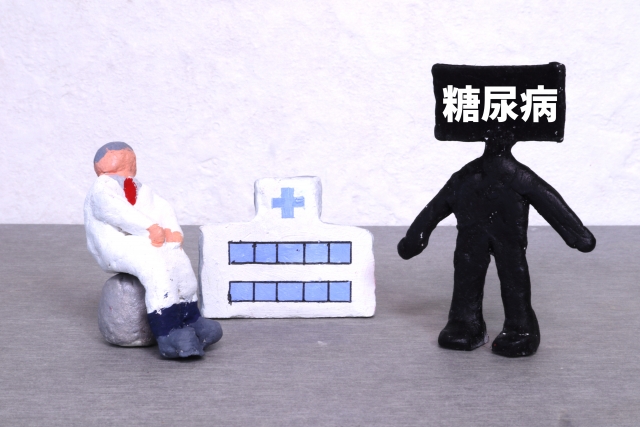
糖尿病による障害の程度が認定基準を満たし、他の諸要件(納付要件・初診日要件)を満たす場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の申請に用いる診断書にはいくつか種類がありますが、糖尿病の場合は『腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用』の診断書を使います。
その診断書において、「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状」であるかどうかを審査されます。
障害年金には「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められていますが、その第15節/代謝疾患による障害にて、以下のように認定基準が示されています。
糖尿病の認定要領
【1】糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。
糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等の慢性合併症が発症、進展することとなる。
糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。
【2】糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
【3】糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
区分ア)無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
区分イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など )
区分ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
区分エ)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
区分オ)身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【4】糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
・内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
また、糖尿病により眼や肢体にも障害を残すことがありますが、これらについては次のように定められています。
・糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。
・糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定する。
・糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
糖尿病の当事者による記録 『糖尿病の哲学』(杉田 俊介 著)を読んで
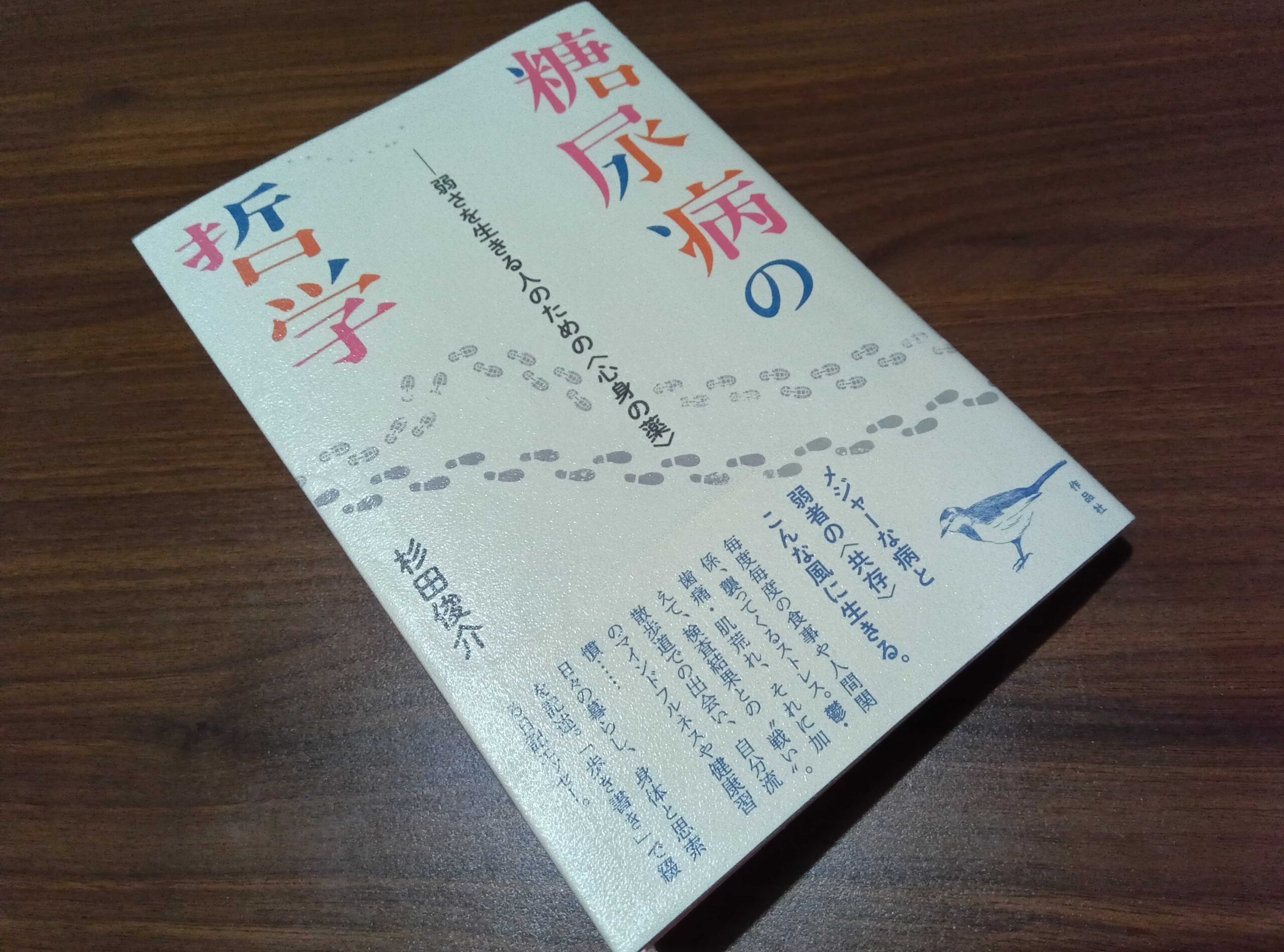
糖尿病の当事者による記録は、他の病気の闘病記と比べて多いものではありません。
わたしは社労士という職業を通じて、糖尿病を患う方の障害年金申請に携わる中で糖尿病と共に生きることの苦労には触れてくることがありましたが、より詳しく当事者目線で語られたものはないかと探すなかで、写真にもある書籍『糖尿病の哲学』(杉田 俊介 著)に出会いました。
冒頭で『この本は、糖尿病患者として、病気の当事者としての、わたしの日々の気持ちや感情の変化を記録したものです。あらかじめ、次の点を断っておきます。これは、糖尿病という病気についての医療的・科学的な情報や知識を、読者の皆さんに伝えるための本ではありません。あるいは、こうすれば病気が改善するとか、こうした治療法によって病気を克服したとか、そうした実践的に役立つ対処法を書いたものでもありません』との宣言があるので、もしかするとこのブログの中で紹介することは著者の望まないことかもしれません。
しかし、私はこの本を読んで気づきが多くありました。
社労士として障害年金業務を通じて糖尿病を患う方との接点もあり、発症までの履歴や発症後の治療状況や病状の変遷についても詳細に伺う機会はありました。
生活上の制限や辛さについてもヒアリングするよう心がけているので、例えば食事に気を遣うストレスのほかにも、低血糖の恐怖、経済的な心配が付きまとうことの不安を抱えていることも知っているつもりでいました。
書籍内でも同様の苦悩は語られており、ただそれらに対して日記形式で日々移ろうリアルな感情がつづられていて、想像以上に恐怖と隣り合わせであることに気づかされました。
著者が強調していたように、個人の感情の記録ではあるかもしれませんが、我々が社労士としてヒアリングする時には感情が整理された状態になっているのに対し、こういった日々の記録、温度感の伝わる記録に触れられたことはとても意義があったと思います。
当事者の方が読めば共感ができるかもしれませんし、糖尿病患者の家族など周囲の人間が読んだ場合にとっても気づきは多いかと思います。気になった方はぜひ読んでみてください。
おわりに

糖尿病と障害年金についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
ご紹介した認定基準をみて該当すると感じたかたは、障害年金の活用も検討してみると良いかもしれませんね。
弊社でも糖尿病での障害年金の申請・需給実績がございますので、ご依頼も大歓迎です。
労働関係のニュースから障害年金の受給の可能性がある病気についてなど、幅広いテーマでお届けしています。
ぜひ、過去の記事もご覧いただけると嬉しいです。

