障害年金の更新時に注意したい「等級変更」のリスクとは

障害年金は一度受給が決定すればずっと同じ内容で支給されると思われがちですが、実際には「更新」という仕組みが存在します。
この更新時に、場合によっては「等級が下がる」「支給停止となる」などのリスクが伴うことをご存じでしょうか?
本記事では、障害年金の更新に際して注意すべき点や、等級変更の仕組み、トラブルを避けるための対策についてわかりやすく解説します。
目次
- ○ 更新とは?|障害年金には有期認定と永久認定がある
- ○ 等級変更のリスクとは?|「下がる」だけでなく「打ち切り」も
- ・どうして等級が変わるのか?
- ○ 医師との連携が重要|「良く書かれてしまう」ことのリスク
- ・医師への伝え方を工夫する
- ○ 更新トラブルを防ぐには?|社労士への相談も有効
- ○ まとめ|更新時は慎重な準備と正確な情報が鍵
更新とは?|障害年金には有期認定と永久認定がある

障害年金は、原則として「障害の状態に応じて支給される公的年金」です。
その障害の状態が一定ではないと考えられる場合、有期認定として数年ごとの更新が求められます。
有期認定と永久認定の違い
・有期認定:数年ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出し、支給継続の可否や等級の見直しを受ける
・永久認定:原則として更新は不要。障害の状態が固定し、今後の回復が見込めない場合に認定される
更新が必要な場合、通常は誕生月の3か月前頃に日本年金機構から「診断書提出依頼書」が届きます。この診断書を期日までに提出し、審査を経て支給継続や等級が判断される流れです。
等級変更のリスクとは?|「下がる」だけでなく「打ち切り」も

更新時に最も多いトラブルが、「等級が下がって年金額が減る」「支給が打ち切られる」といったケースです。
特に、精神障害や発達障害など、状態の評価が医師の主観や記載内容に左右されやすい場合は、診断書の書き方一つで結果が変わることもあります。
どうして等級が変わるのか?
障害年金の等級は、基本的に「日常生活能力」や「労働能力」に基づいて判定されます。
更新時の診断書に「改善が見られる」「以前より支援の必要度が低くなっている」と読み取れる記述があると、2級→3級、3級→支給停止といった決定がされることがあります。
また、「通院状況」「服薬状況」「就労の有無」などの情報も審査に影響するため、生活状況に変化があった場合は、医師への共有が特に重要です。
医師との連携が重要|「良く書かれてしまう」ことのリスク
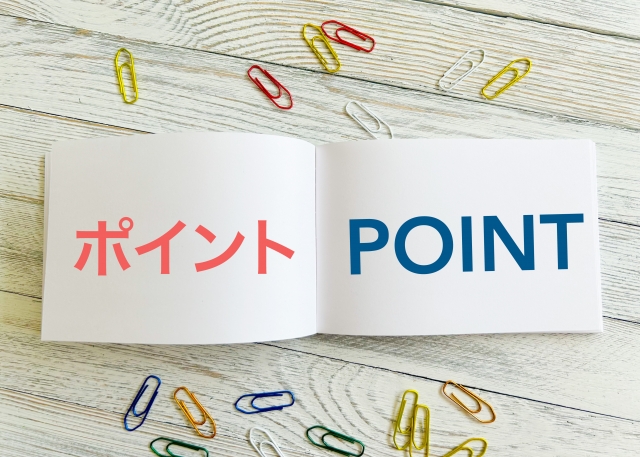
更新時の診断書作成で多い誤解が、「なるべく元気に見せた方が良い」という考え方です。
ですが、これは障害年金の審査においては逆効果になる場合があり、本来受けられるはずの等級が下がってしまう原因となります。
医師への伝え方を工夫する
・「普段の生活で困っていること」を具体的にメモにまとめて医師に伝える
・調子の良い日ではなく、平均的または悪い状態をベースに説明する
・家族や支援者と一緒に受診し、第三者の視点も診断書に反映してもらう
医師にとって、日常のすべてを把握するのは難しいため、診察時にしっかりと情報共有を行うことが、適正な診断書作成につながります。
更新トラブルを防ぐには?|社労士への相談も有効

等級変更や支給停止といったリスクを最小限に抑えるには、更新の準備を計画的に進めることが重要です。
更新前にやっておきたいこと
・前回の診断書と現在の生活状況を照らし合わせる
・生活上の困りごとを記録しておく
・医師と十分なコミュニケーションを取る
・状態が重く、伝達が難しい場合は、社労士に相談する
特に、過去に不支給や等級変更の経験がある方や、初めての更新を迎える方は、障害年金に詳しい社労士に事前に相談することで、安心して準備を進めることができます。
まとめ|更新時は慎重な準備と正確な情報が鍵

障害年金の更新は、ただの「継続手続き」ではなく、内容によっては生活に大きな影響を与える大切な節目です。
医師との連携、診断書の内容、日常生活の実態の共有――こうした点を丁寧に行うことで、不要な等級変更や支給停止のリスクを減らすことができます。
更新に不安がある方や、過去に等級変更でお困りだった方は、専門家への相談をぜひご検討ください。
▼当事務所の紹介動画はこちら▼
当事務所では、障害年金の新規申請だけでなく、更新対応に関するご相談も承っています。
更新の準備や診断書の確認など、お一人では難しい内容も専門家がサポートいたします。

