自閉スペクトラム症と障害年金:申請のコツと注意点
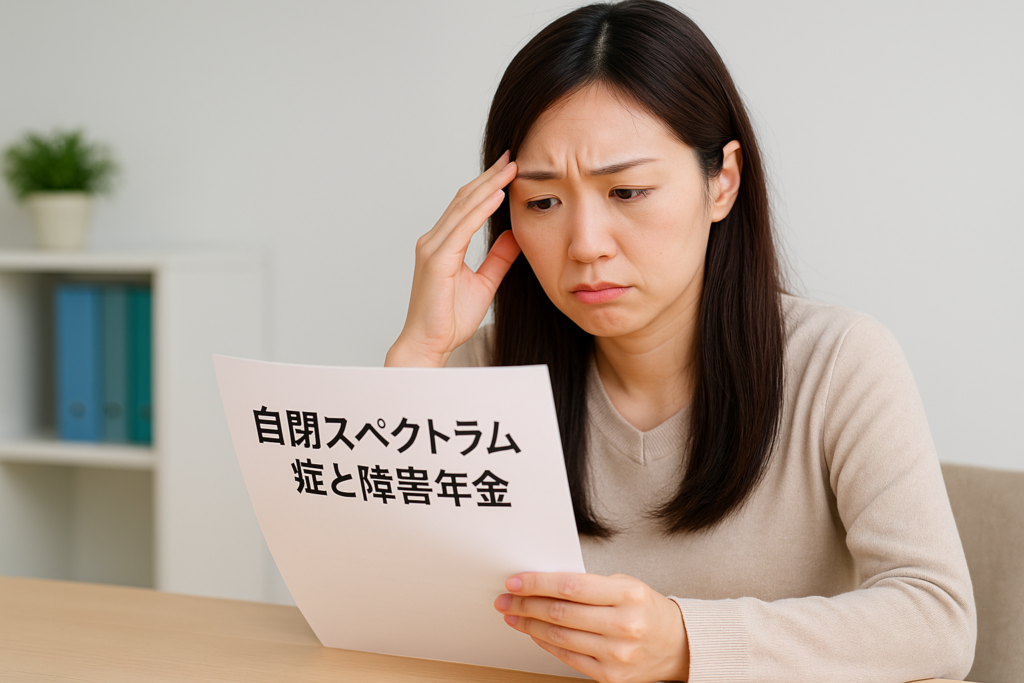
自閉スペクトラム症(ASD)は、発達障害の一つとして知られ、近年ではその認知度も高まってきました。しかし、障害年金の申請においては、精神障害の中でも特に認定の難易度が高い※とされており、慎重な準備が求められます。
(※難易度が高いとされる理由については、本文後半で詳しく解説します)
この記事では、自閉スペクトラム症による障害年金申請におけるポイントと注意点を、実務経験を踏まえてわかりやすくご紹介します。
目次
- ○ 自閉スペクトラム症とは?障害年金の対象になるの?
- ○ 自閉スペクトラム症で障害年金を申請する際の注意点
- ○ 障害年金の等級とASDの現実的なライン
- ・※なぜASDの障害年金申請は難しいのか?
- ○ まとめ
自閉スペクトラム症とは?障害年金の対象になるの?

自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:ASD)は、社会的コミュニケーションや対人関係における困難、強いこだわりや感覚の過敏さなどを特徴とする発達障害です。
ASDは先天的な要因によるものであり、知的能力にばらつきがあるのも特徴です。
知的障害を伴わない「高機能自閉症」や、「アスペルガー症候群」と呼ばれていたタイプも、現在はすべてASDに含まれます。
障害年金の対象になるかどうかは、診断名だけでは判断されません。
日常生活にどれほど支障があるか、社会的適応がどれほど困難かが、年金の等級を左右する重要な判断基準になります。
自閉スペクトラム症で障害年金を申請する際の注意点

1. 診断書の内容が結果を大きく左右する
障害年金の審査では、「診断書」が最重要資料となります。
特に精神の障害に関する診断書では、「日常生活能力の判定」や「具体的な支援の必要性」の記載が詳細に求められます。
医師によって記載の内容が大きく異なるため、申請前に記載内容を丁寧に確認し、必要に応じて補足資料を用意することが重要です。
2. 初診日の証明がカギになる
障害年金を受給するには、「初診日」を明確に証明する必要があります。
自閉スペクトラム症の場合、小児科や療育センターなどでの記録が残っていないケースもあり、初診日の証明が困難になることも少なくありません。
医療機関の記録が不足している場合には、学校の通知表や療育手帳の取得記録、福祉サービスの利用歴など、あらゆる間接資料を活用する必要があります。
3. 本人の自覚が乏しい場合の対応
ASDの方の中には、自身の困難を自覚していない方も多くいます。
その場合、自己申告ではなく、家族や支援者からの客観的な情報を添えることで、生活上の困難さを正確に伝えることができます。
障害年金の等級とASDの現実的なライン

障害年金には1級・2級・3級(厚生年金のみ)があります。
1級は日常生活がほぼ自力で営めない重度の状態であり、ASD単体での認定は極めてまれです。
2級であっても、「社会的適応の困難さ」「他者の支援がなければ生活が成立しない程度」の支障がなければ、認定されるのは困難です。
たとえ診断名があっても、軽度と判断されれば不支給となるケースもあります。
※なぜASDの障害年金申請は難しいのか?
自閉スペクトラム症が「難しい」と言われる背景には、以下の3点があります。
● 見えにくい障害である
ASDは外見上の障害が目立ちにくいため、「本当に困っているかどうか」が他人からは分かりづらいという特性があります。
そのため、診断書や申立書での丁寧な説明が不可欠です。
● 症状のばらつきが大きい
ASDは「スペクトラム(連続体)」という言葉の通り、個人差が非常に大きい障害です。
年金の審査では、その人固有の困難さをいかに具体的に伝えられるかが問われます。
● 有期認定が多く、更新のたびに審査がある
自閉スペクトラム症の年金は「有期認定」となることが多く、1〜5年おきに更新が必要です。
更新審査では、等級の引き下げや支給停止のリスクが常に伴います。
まとめ

自閉スペクトラム症での障害年金申請は、診断名だけでは判断されず、「日常生活の困難さ」や「社会的適応の度合い」が厳しく審査されます。
そのため、診断書の内容や証拠資料の整備、本人の状態を正確に伝える工夫が求められます。
ASDでの障害年金申請は、診断書の確認、初診日証明、申立書の記載など、専門的な知識と丁寧な準備が求められます。
経験豊富な社会保険労務士に相談することは、申請の不備や不支給のリスクを回避しやすくなるのが最大のメリットです。
ご本人やご家族が不安や負担を感じることなく、適切な支援を受けられるよう、専門家の力をぜひ活用してください。

