ギフテッドが抱える生きづらさ。“天才”が抱える苦悩とは

ギフテッドは、最近ては映像作品などで登場人物の個性として扱われることが多く、そういった影響から「ギフテッド=天才」というのが一般的なイメージではないでしょうか。
しかし、肌の色にしろ体形にしろ、そして能力にしろ、周囲との “違い” に私たち人間は悩みを抱くものです。
もちろん多様性が知られるようになった現代では、他との違いを個性として互いに認めあうことの大切さは認識されつつあります。
それでも当事者は違いや個性を必ずしもポジティブに変換できるとも限らず、ネガティブな側面に悩まされることもあるものです。
このブログでは、ギフテッドの華々しい側面だけでなくギフテッドゆえの困難にも触れて、理解を深めることを目的にまとめています。
ぜひ、最後までお読みください。
目次
ギフテッドの定義はあるのか?
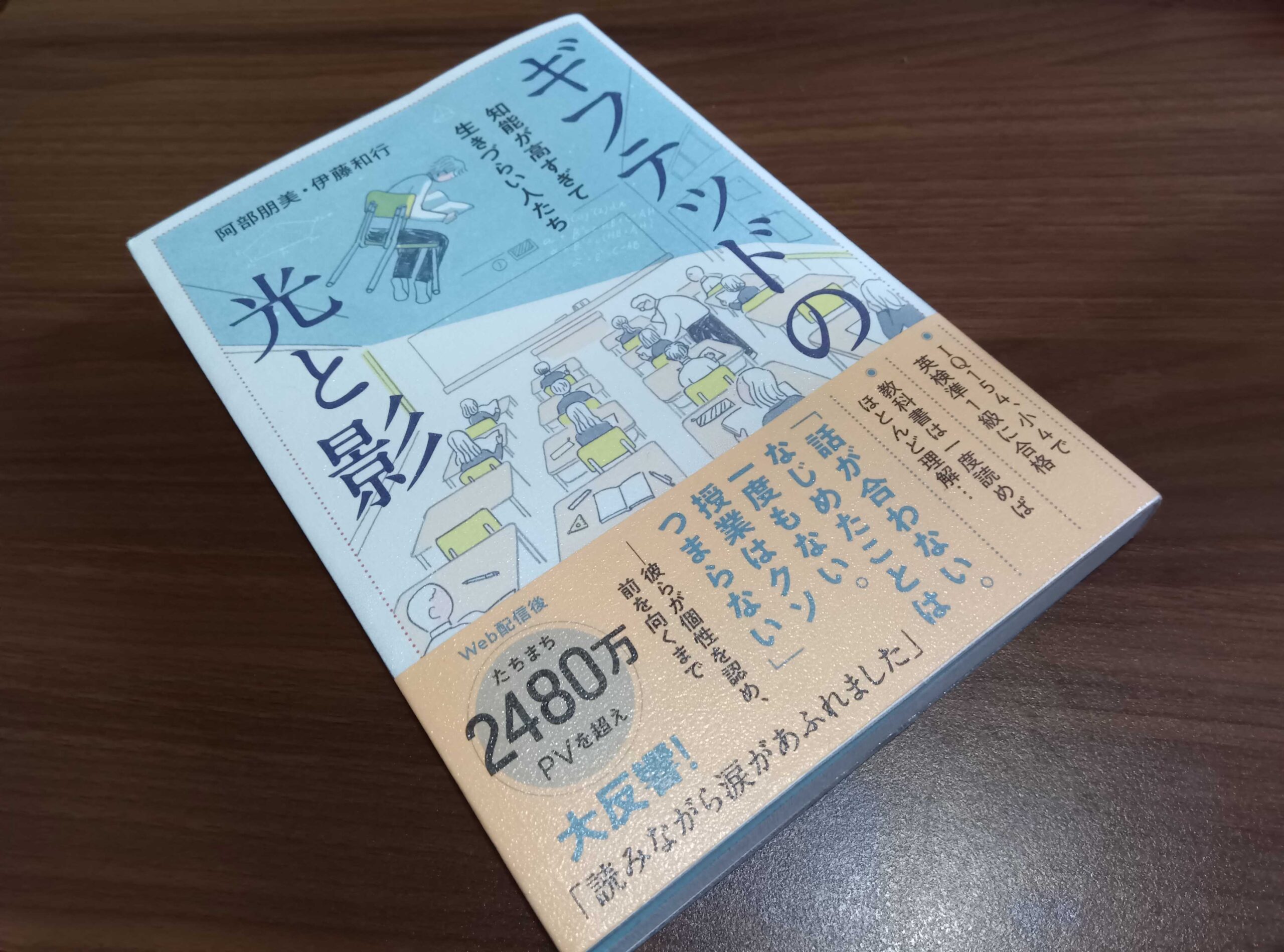
ギフテッドという言葉は知られるようになったものの、一体なにをもってギフテッドと定義づけるのでしょうか。
写真にもある、『ギフテッドの光と影 知能が高すぎて行きづらい人たち』(阿部朋美・伊藤和行 著)によると、日本において現時点では「具体的な定義づけは無い」と紹介されていました。
2021年にギフテッド(特異な才能を持つ子どもたち)への支援を検討する有識者会議が文部科学省によって発足されたものの、具体的な定義づけは見送られ、翌22年には「IQ(知能指数)などをもとにして才能を定義すると、高IQの人を選抜する動きが出てくる」として、改めて「定義はしない」と結論づけられたようです。
そもそも日本はギフテッド教育に関しては後進国であり、日本がゆとり教育を導入し始めたころ、世界ではすでにギフテッド教育がトレンドとなっていました。
そんな他国でのギフテッドの定義は様々で、IQ130以上とする国もあれば、独自の基準を設ける国もあります。
このように日本に明確な基準が無いだけでなく、世界をみても統一の基準があるわけではないものの、とある海外の研究では「様々な才能の領域で3~10%(つまりクラスに1~3人程度)」の割合でギフテッドは存在するとされており、案外身近な存在であると感じさせられます。
また、ギフテッドの大半(約9割)を占めるのがIQ120~130の人であるとされており、映画やドラマで見るような超人的な天才(IQ160超)はギフテッドの中でもごくごくわずかな存在のようです。
一説にはIQが20違うと話が通じない(合わない)ということも耳にしますが、一般的なIQの平均値とされる100と比べても、ギフテッドといわれるIQ120~130の方とはIQの差があるため、コミュニケーションに苦痛を感じることが想像できます。
次の章ではより具体的にギフテッドの方が抱える光と影に触れていきます。
ギフテッドと発達障害 “2E”とは何か?
ギフテッドの生きづらさ(影の側面)については次の章で詳しく触れていますが、ギフテッドの困難さを知ると発達障害とどう違うのだろうか?という問いにたどり着きます。
たとえば、教室での問題行動と捉えられがちな、授業中にぼーっとしている等の無気力感、あるいは授業を中断させるほどに質問を重ねる好奇心などは、その様子だけを切り取ってみると確かに一部の発達障害とも重なる部分があるかもしれません。
しかし、発達障害が脳の機能障害に問題があるとされるのに対し、ギフテッドの場合は限られた状況や場面に限ってこのような行動がみられるとされています。
『ギフテッドの光と影 知能が高すぎて行きづらい人たち』では「不適切とされる言動について本人なりに筋の通った説明ができるか、本人の意図が背後にあるかが、障害を伴うものかどうかの判断ポイントになる」と説明されています。
このようにギフテッドと発達障害には違いがあるものの、それらが共存しないかといえばそうではありません。
ギフテッドでありながら発達障害を抱えるケースもあり、このように才能と障害が共存することで凸凹に対するそれぞれの支援(2つの支援)を要するといったところから、【twice-exceptional】略して【2E】と呼ばれます。
ギフテッドの光と影

ギフテッドの光と影、これは上の章で紹介した書籍タイトルをそのままお借りしてブログの見出しとしました。
というのも、書籍内でもメインテーマとして取り上げられていることですが、ギフテッドは「なんでもできる天才・超人」のイメージが先行しすぎていて、実生活の困難については認知が広がらず、むしろ誤解される(有能であると主張してくる、わがままだ等)ケースが多いのです。
ギフテッドは多くの場合幼少期に何かしらのきっかけで気付くとされますが、大人になってから自身がギフテッドだと知り、これまでの生きづらさに納得したというケースもあります。
何か特定の領域で才能を発揮することを光とするならば、影としてどんな困難があるのでしょうか。
ここでは、幼少期と成人後に分けてギフテッドが直面する”影”の側面に触れていきたいと思います。
ギフテッドの幼少期
ギフテッド教育が日本ではまだまだ遅れていることは先に述べた通りですが、幼少期に周囲との不適応を起こすとあとの人生にも多大な影響を与えることは想像に容易いことと思います。
知的な才能を持つギフテッドの場合、平均的に2~4学年分の知的レベルが進んでいるとされています。
繰り返し参考元としてご紹介している『ギフテッドの光と影 知能が高すぎて行きづらい人たち』でも「小学6年生が小学2年生のクラスに所属していること、高校1年生が小学6年生のクラスに所属していることに相当します」と表現されており、大人の2~4歳ならまだしも、幼少期や学生時代の2~4歳(学年)の大きさを実感させられます。
日本では後れを取る子どもに対しての特別支援は進んできたものの、周囲より進んでいる子への支援は手厚くありません。
そんな中、授業を退屈と感じてしまい、同級生とも興味関心が合わず会話が弾まないとなると、浮いた存在になり、学校への足が遠のくのも無理はありません。
知的好奇心から教師に質問をしても、ただでさえ仕事の多い教師にとっては対応が難しく、質問が度重なると“嫌がらせ”と誤解して受け取れるケースもあるといいます。反対におとなしく授業に参加しても退屈なため、ぼーっとすると「やる気がない」と誤解されます。
また、平均的で画一的な教育を良しとする中ではひとつの問題を解くにしても唯一の解法だけが正解とされ、独自の視点と方法で答えにたどり着いても注意を受けるといった理不尽さを味わうこともあるようです。
大人でも関心レベルの異なる研修や退屈な会議の参加は苦痛を伴うものです。まだまだ義務教育を中心とした子供の世界では毎日元気に登校することが良しとされ、周囲に理解が無い限り休む自由すらないことも珍しくありません。
そういった背景もあってか、他国に遅れを取りながらも、日本においても一部で英才教育・ギフテッド教育に似た取り組みが進められています。
しかしながらそれらは共通して「子どもの埋もれた才能を引き出したいという思いが、子どもや保護者らに、優劣の感覚や行き過ぎた能力主義の意識を与えてしまった」という反省を抱えながら試行錯誤していることが参考書籍(ギフテッドの光と影 知能が高すぎて生きづらい人たち)では紹介されていました。
ギフテッドが大人になると
ギフテッドとして生きることは、華々しい成功だけではないことはここまでで述べた内容で理解していただけたと思います。
また、ギフテッドではない人と同じで、全てのギフテッドが幼少期に恵まれた環境に身を置けるわけではありません。
では、自由度が高まる成人後はのびのびと生きることはできるのでしょうか?
ここでも『ギフテッドの光と影 知能が高すぎて行きづらい人たち』を参考に、大人になったギフテッドの事例について理解を深めたいと思います。
本書によると「ギフテッドの特性として、複雑で論理的な洞察力や正義感などがあることがこれまでの研究で指摘されている」そうで、この能力を会社は歓迎し重宝すると思えます。
しかしながら、周囲との調和や協調性が重んじられる傾向にある日本の会社の中で、ギフテッドは異端な存在になってしまうことがあるようです。
本書において、当事者である吉沢拓さんの次の言葉がとても印象的でした。
「ギフテッドはなんでもできる夢の人材ではありません。優秀なのではなく、特殊ということを知ってもらいたいです。扱いづらい点もあるかもしれません。会社として必要な能力と思ってもらい、能力を守って活かす方法を考えてもらえれば、お互いに良い結果を与え合う関係になれるのではないでしょうか」
おわりに

ギフテッドをテーマに、ご紹介した書籍から新たに学んだことも交えつつご紹介しました。
冒頭でも述べましたが、ギフテッドはドラマや映画の登場人物の個性として見かけることが少なくありません。
子どもの頃から神童扱いで周りから一目置かれる存在、といった描写も“あるある”かと思います。
実際に私もギフテッドに対し天才というイメージだけを抱いていました。しかし、少し前のクールのドラマ「マイダイアリー」でギフテッドならではの苦悩が描かれていたことが、ギフテッドの光だけでなく「影」にも関心を持つきっかけとなりました。
そこから書名が『ギフテッドの光と影』と名付けられた書籍を手にする機会があり、今回のブログテーマに選定するに至りました。
このブログがギフテッドを多面的に理解するきっかけにつながれば幸いです。

