“働くこと”について考えるきっかけをくれる!社労士オススメ書籍

「働く」と密接な職業である社労士。職業柄なのか、日ごろから働くことをテーマにしていたり、働くことについて考えるきっかけを提示してくれる書籍をたびたび手に取ります。
このブログでは、最近私が読んだ中でおススメしたい書籍を何冊かご紹介しています。
新年度から数か月たって、慌ただしさが少し落ち着いたころ。ふと「この働き方で良いのかな…」と疑問を抱くようになる方も多いのではないでしょうか。
そんな方にも、ご紹介している書籍は気づきがあったり共感があったり励まされると思います。
ぜひ、最後までお読みいただけると嬉しいです。
目次
- ○ 働くことはあなたの人生や生活でどんな位置づけですか?
- ○ 働くことについて考えるきっかけをくれるオススメ書籍
- ・なぜ働いていると本が読めなくなるのか/三宅 香帆
- ・おいしいごはんが食べられますように/高瀬 準子
- ○ おわりに
働くことはあなたの人生や生活でどんな位置づけですか?

働くことに対するスタンスや、生活ひいては人生での位置づけって人それぞれですよね。
「24時間戦えますか」というCMが流れていた頃のようにひたむきに“企業戦士”に擬態する時代は去り、「ワークアンドライフ」といった言葉を通じて認識されているように、個々人が自分の理想とする働き方を求める時代になりました。
近年の流れとしては、「働き過ぎない」ことを推奨する一方で、リスキリングに代表されるような、スキルアップを通じた自己実現を後押しする傾向にありますよね。
自らのキャリアを自らの意思で設計していく姿勢が求められるなか、あなたにとって「働くこと」の位置づけはどんなものでしょうか?
最近私がハッとさせられたのは、益田ミリさんの同名マンガをドラマ化した『僕の姉ちゃん』での「仕事は人生のすべてではないが、仕事があると思うと乗り越えられることもある」というセリフです。
いかにプライベート時間を確保するか、いかに余暇を充実させるかといったことにフォーカスされがちな現代ですが、自分には仕事があるということに支えられる瞬間があるのもまた事実だなと感じました。
つまりは「バランス」が大切だというのは「ワークライフバランス」という言葉からもわかることですが、“ワーク”と“ライフ”の比率を何対何にすれば均衡がとれるのかは人によって異なるのではないかとも思います。
そこで、働くことについて考えるきっかけを提供してくれる書籍を紹介することで、自分にとっての最適な均衡はどこにあるのかといった問題に向き合う時間につながればと思い、このブログを書くことにしました。
働くことについて考えるきっかけをくれるオススメ書籍

働くことについては、これまでも「静かな働き方」や「キャリア形成」「マミートラック」といった切り口でブログでご紹介したことがありました。
これらの過去ブログでも参考書籍をご紹介してきましたが、メインテーマとしたものだけでなくサブテーマにしたものまで含めると、働き方にまつわる要素を含む書籍はたくさんあります。
私も社労士という職業柄、それらの書籍には興味があり手にとることも多いのですが、その中でもぜひみなさんにも読んでいただきたいものをご紹介します。
なぜ働いていると本が読めなくなるのか/三宅 香帆
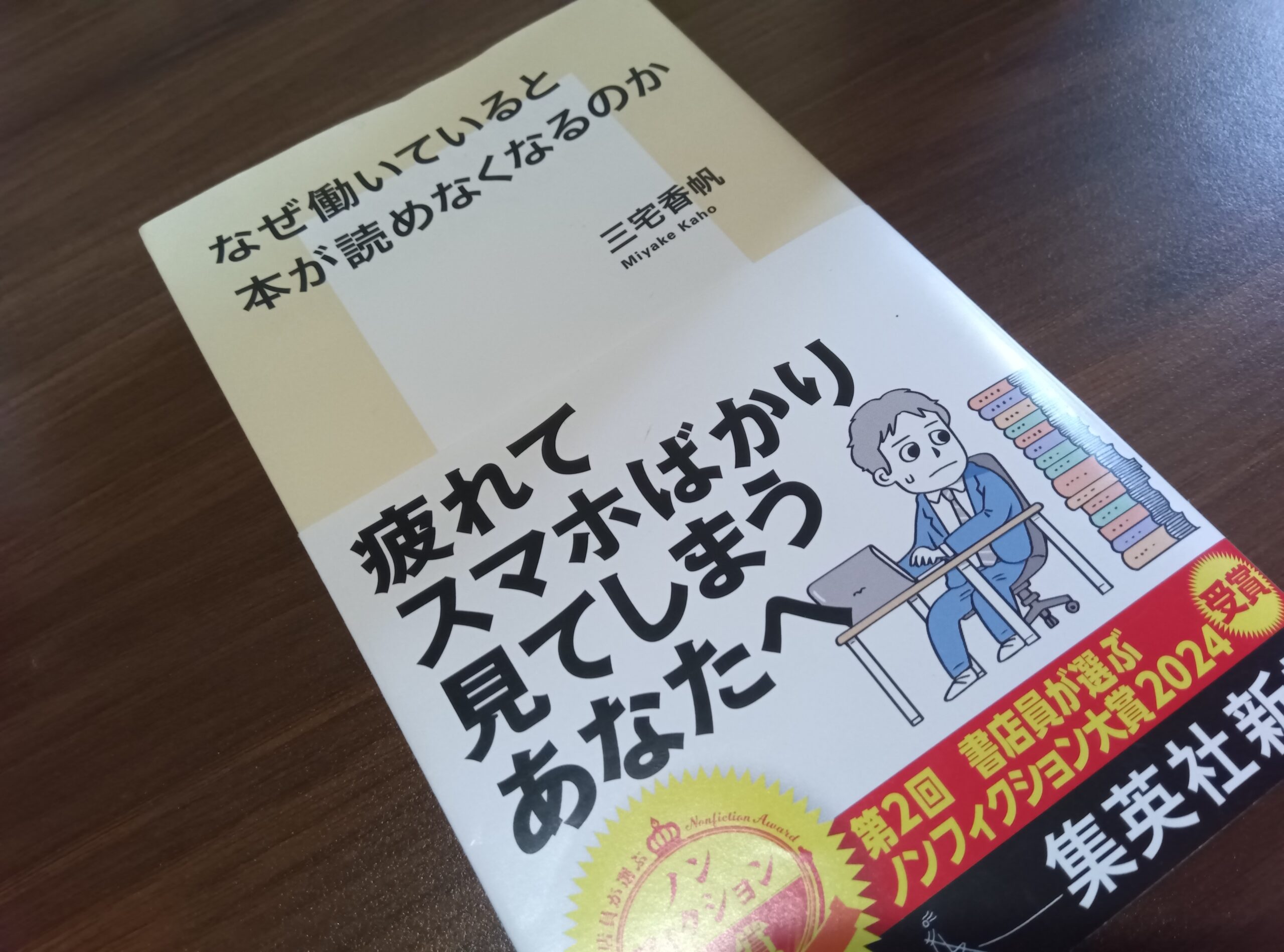
書評家の三宅香帆さんが会社員時代に多忙を極める中で読書が遠のいた経験を基に、読書(本)を通じて、働きかたの変遷について教えてくれます。
「働き方改革」が叫ばれるよりも前、全身全霊で会社に尽くすことが良しとされていた時代と現代では読まれている本にも違いがあったりと、読書から紐解く労働史は社労士としても興味深い内容でした。
読書という切り口から労働史を辿りつつも、タイトルにある『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の「読書」が指す意味としては読書に限らず各々が大切にしている趣味の時間を指しているので、自分が失いかけている趣味の時間に置きかえて読むと、全社会人に刺さる内容だと思います。
おいしいごはんが食べられますように/高瀬 準子
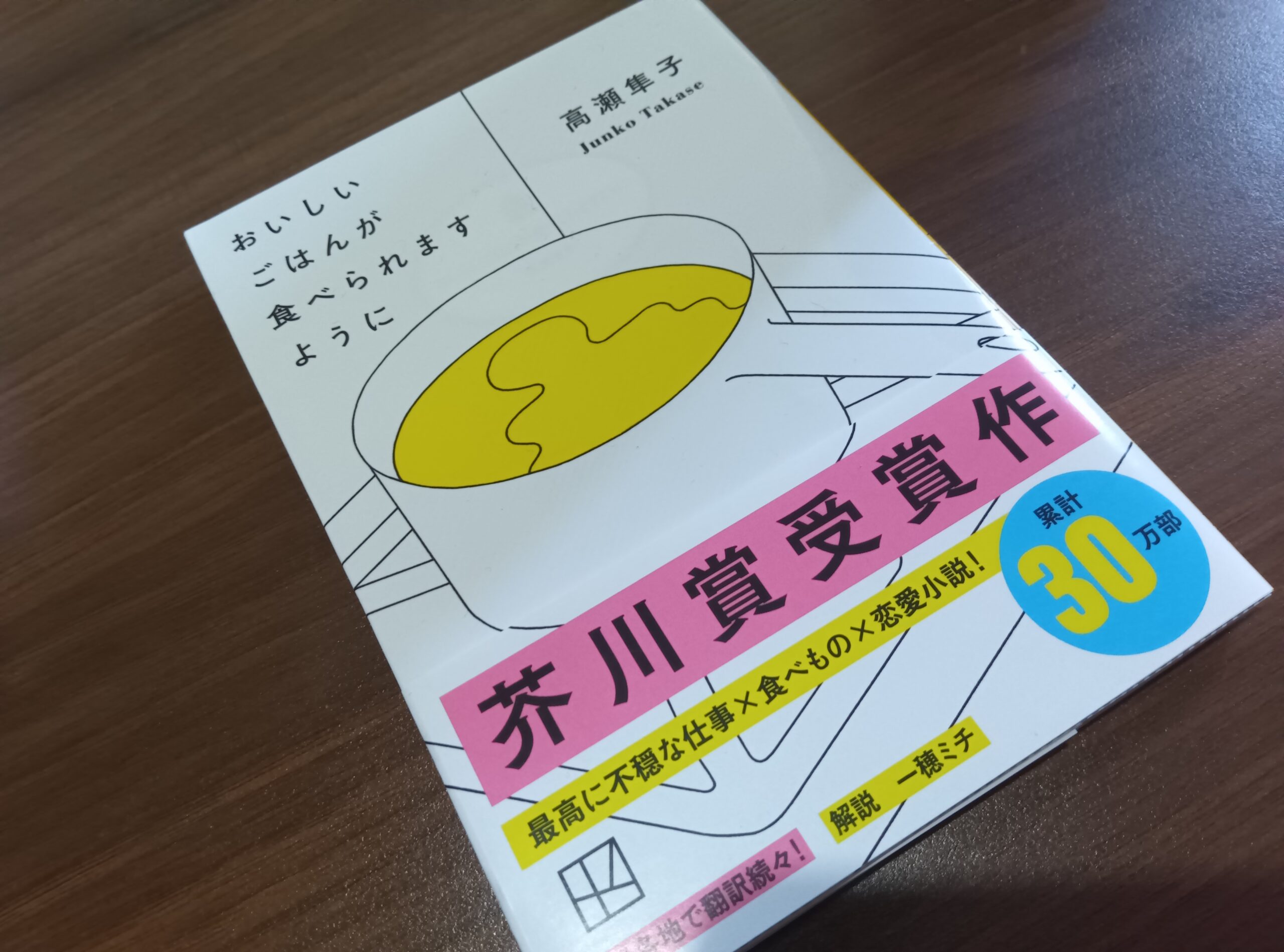
この作品は「働き方」をメインテーマにしたものではないのですが、キャラクターのひとりとして誰しもが共感を覚える「ごまめ社員」がかなりの解像度で描かれていて、主人公がその人に対して抱くモヤモヤした感情を通じて間接的に「働き方」について考えるきっかけを提示してくれます。
主人公と、このごまめ社員の仕事に対する姿勢(もっといえば生き方のスタンス)は真逆といってもいいほど異なります。
私は主人公のほうが感情移入できたので、ごまめ社員に対するやり場のないモヤモヤに激しく共感してしまったのですが、読後に「でもこれって働き方の多様性による違いがあるだけだよな」と思い直しました。
ごまめ社員として描かれている女性は、面倒な仕事からは逃げがちで少しの体調不良ですぐに早退してしまうけれど、手作りのお菓子を周囲に配るなどのいわば「生存戦略」には抜かりがないなど、仕事にはフルコミットしないながらも職場での人間関係は波立たせまいとする努力は伝わってきます。
「ブリリアントシャーク」といった言葉でも認知されていますが、仕事に対する意欲があっても人間性に問題のあるタイプもいます。そういったタイプと比べると彼女のようなひとは、実際に作中でもそうであるように、度重なる早退をして周囲に仕事のしわ寄せがあったとしても「しょうがいないよね」と許されてしまう…。
このような状況に対して、主人公のように仕事に対して多少の自己犠牲を払ってでも向き合うタイプは、やりどころのない不満を覚えます。
この働き方に対する姿勢の違いをきっかけに生まれた感情が物語を展開させていくのですが、読後は登場人物に照らし合わせて自然と自分の働き方について考えること間違いなしです。
おわりに
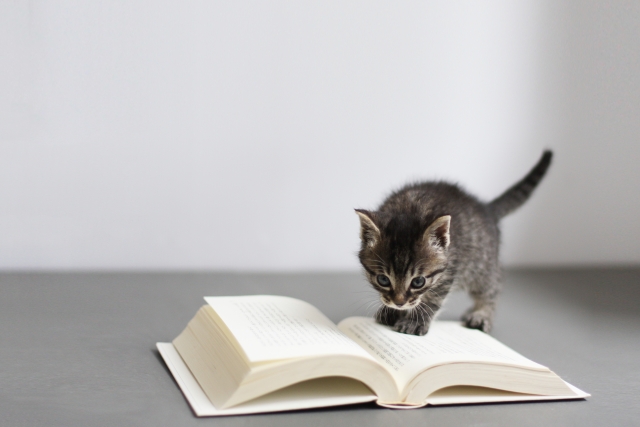
働くことに対する価値観が複雑になってきた現代で、働くことについて考えることはエネルギーを使うことかもしれません。それゆえに無意識に避けてしまうこともあるのではないでしょうか。
確かに、「働くことについて考えろ」と言われると身構えてしまうかもしれませんが、偶然手にとってみた作品を通じてふいに自分の働き方に対して問題提起されたような気持ちになり、結果として自分の働き方を見つめなおす機会を得るのはとても良いことのように思います。
このブログを読んでくださった方が、紹介した書籍に関心を持ち、さらには読後に自身の働き方について考える時間を持てたなら嬉しく思います。
\こちらもおススメ/
日本で多く取り入れられているユング派(ユング心理学)をテーマにしたブログでご紹介した書籍です。
ためこみ症をメインテーマに、みんなが知っている偉人も生きづらさを抱えていたことが知れる本としてブログ中でご紹介しました。

